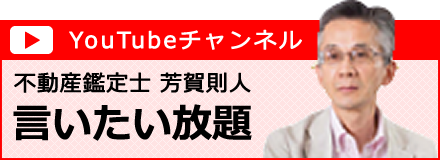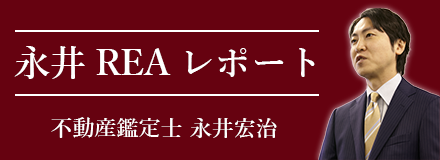東京アプレイザル・不動産鑑定士の永井宏治です。
今回のREAレポートは「相続における鑑定評価の醍醐味」についてのお話です。
不動産鑑定評価はさまざまな依頼目的があり、その目的に応じた不動産の価格または賃料を求めることが主たる仕事です。そのさまざまな依頼目的の中でも相続税申告に関する依頼目的のものが私個人としては一番やりがいを感じます。東京アプレイザルも「相続に強い」鑑定事務所というのを売りにしておりますが、改めて何が醍醐味と言えるのかを私なりに考えてみましたので、下記に挙げてみます。
-
- 税務の知識が必要となるため、(税理士さんほどまではいかなくても)実務の中で税務の知識も身につける必要がある。
- 税務の知識がある鑑定士は税理士さんから信頼されやすく、さらに信頼関係を築いて相続人のためにお仕事をすることで「一緒に依頼者のお役に立てている」という実感を得られる。
- 「評価単位」という鑑定評価の分野にはない税務の考え方が不動産調査や評価をとても奥深いものとしている。また、CAD作図分野も同様で、精緻で説得力のある図面を描こうという動機付けにもなる。
- 上記1、3に関連して、相続の土地評価に関して多くの裁決事例があることでより多くのことを学ぶ必要があり、税務評価の奥深さについて追究しがいがある。
- 単に申告のための価格を求める鑑定評価のみならずコンサルティング業務につながる可能性がある。
- 税効果という観点から「鑑定評価が依頼者のお役に立っている」という感覚が他の評価よりも大きい。
- 良い意味で珍しい対象不動産(評価難易度が高い不動産)に出会うことが多い。
このようなところでしょうか。私個人としては2、3、4が特に大きいかな、と考えています。相続に関する鑑定評価の実務を結構な年数行い、著書も出版させていただき、それなりに経験は積んできていると思う反面、未だに難しい案件に出会うことも多く、本当に日々勉強を継続していかなければ、と感じます。
若い(20~30代半ばくらい)鑑定士試験合格者や鑑定士登録したての人でこのREAレポートを読んでいるという方はあまりいないと思いますが、少しでもそのような人の「不動産鑑定士としてどのような方向に進みたいのか」ということの参考になればと思います。私個人としては相続に関する鑑定評価は大変やりがいがあるため、是非若い不動産鑑定士にも参入し、相続の場で不動産鑑定士の活躍が増えれば良いなと思います。
最後に、4月から始まった「相続土地評価アカデミー」が9/11(木)で15講座(不動産調査編、財産評価重要論点編、鑑定評価実例編)終了いたしました。多くの方にご受講いただいたことに感謝申し上げます。
また、「相続土地評価アカデミー 裁決事例考察編」が今秋開始予定です。より濃い内容をお届けできればと思います。
詳細が決定しましたら、改めてご案内させていただきます。是非こちらもご受講いただければ幸いです。



![[月いちコラム]芳賀則人の言いたい放題!](/wp-content/uploads/side-blog02.png)
![[対談ブログ]こんにちは、芳賀則人です](/wp-content/uploads/side-blog03.png)