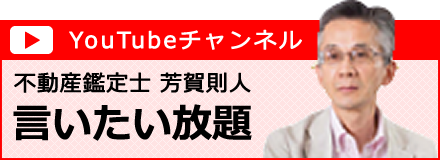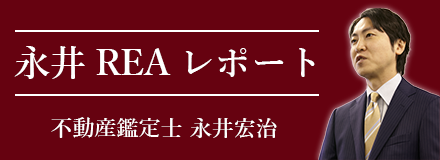東京アプレイザル・不動産鑑定士の永井宏治です。
今回のREAレポートは「特別の事情」についてのお話です。
「特別の事情」とは相続税財産評価において財産評価基本通達による評価を行わない場合の事情をいいます。不動産に関して換言すると、「土地評価において不動産鑑定評価を適用する事情」ともいえます。
昨年12月に拙著「相続税土地評価における鑑定評価実例と裁決事例考察」を上梓してから、この「特別の事情」を意識させられることが増えました。意識させられる、というよりは「意識せざるを得なくなった」という方が適切かもしれません。
私個人としては、通達評価額>時価(鑑定評価額)となる可能性がある場合に、直ちに鑑定評価を適用することが必ずしも良いことだとは考えていません。やはり相続税の世界では「通達評価が基本」であり、「通達では反映しきれない減価」と認められる箇所がなければ、鑑定評価で「この価格が時価です」と主張したところで「いや、相続税では通達が時価とみなされています」と却下されてしまうでしょう(この辺りのことは拙著の序論にて合理性欠如説、合理性比較説の比較で述べています)。
したがって、不動産鑑定士も相続税申告において、鑑定評価による時価を主張する場合には通達評価も勉強し、「通達評価では反映しきれない減価」とはどのような部分なのかを把握した上で、依頼をいただく税理士さんや提出先である税務署に対して「特別の事情」をきちんと説明できるようにすべきでしょう。
ただし、評価実務においては壁にぶつかることも多くあります。相続土地評価で下限値だと考えられる価格を鑑定評価で出したとしても、その後に売買された価格は鑑定評価額をさらに下回る、ということもあります。鑑定評価に向いている土地、と判断したとしても通達評価で考えると、あえて鑑定評価を使わなくとも通達評価で十分な下限値を得られる場合(例:通達の減額要素及び造成費控除でマイナス評価になる市街地山林を純山林評価とするケース等)もあります。
また、ある程度経験を積んでいても、不動産は同じものが2つとなく、利用の状況もそれぞれ異なるため、都度頭を悩ませることとなります。不動産価格というものはなんと難しいものか、とつくづく思います。
そのような中でも、相続税土地評価において鑑定評価を適用しようとするならば、「特別の事情」を考え抜く必要があります。
来月11月13日(木)、この「特別の事情」をテーマとして税理士・笹岡宏保先生と対談セミナーを開催させていただきます。今年1月にも、笹岡先生と対談セミナーを行わせていただきましたが、今回もこのような機会を設けていただきました笹岡先生に深く感謝申し上げます。
是非多数の方々のご参加をお待ちしております。
秋のスペシャルセミナー「鑑定評価実例・裁決事例から考える【特別の事情】」
詳細はこちらからご覧ください。
https://tap-seminar.jp/seminar.php?keyno=2786
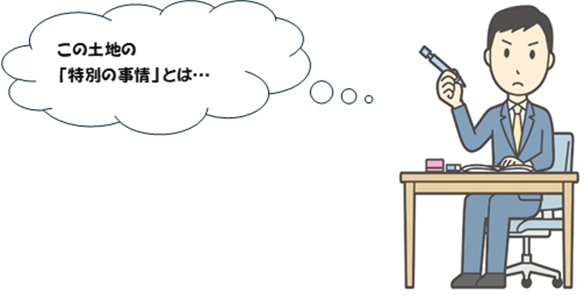


![[月いちコラム]芳賀則人の言いたい放題!](/wp-content/uploads/side-blog02.png)
![[対談ブログ]こんにちは、芳賀則人です](/wp-content/uploads/side-blog03.png)