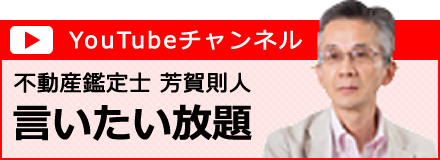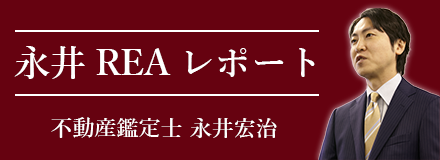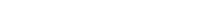相続コンサルタントで最も悩ましいのが報酬のもらい方ではないでしょうか。
士業(弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士等)はその点、自分の業務報酬がある程度の水準(相場といって良い)が保たれているので、比較的請求しやすい立場にあります。これは逆にいうと、これらの士業は相続コンサルタントとはいわない(名乗れない)といっても過言ではないかもしれません。先生の業務でもらう報酬はつまり本業でしょう、コンサルじゃないでしょうと。
「相続業務」というのは、多くの分野で士業が関わる事が存在します。しかし、士業がいれば全て問題が解決するという訳でもありません。士業は縦割りであり横のつながりが希薄になります。例えば、相続の分割協議で揉めた場合に、不動産の評価では民法と税法では全く反対な解釈さえあるのです。ここで、弁護士と税理士しか存在しない場合(あるいは解決するための人物)は動きが取れない状況に陥るかもしれません。ところが、不動産業で相続コンサルティングマスターや、相続診断士を保有する人がいたとします。
「本件は不動産鑑定士による鑑定評価の力が必要だ」とアイデアを出せば、一気に解決に向かうことなどもあり得るのです。
士業のメンタリティとして、自分の業務が一番だと思っている人が案外多いのです。それは仕方ありません。その弊害として客観的な判断を下せなくなります(つまり岡目八目的な判断です)。
相続コンサルタントは様々な業務の勉強をしている強みで、解決方法を見出すことが出来るのです。つまり、凝り固まった状況をほぐす役割です。それには高度な知識と経験が必要です。ついでに人生経験などもです。(80歳のお父さんが30歳そこそこの若造のアドバイスなんか素直に受け入れませんよね)。
さらにいえば、分割協議の業務は弁護士の専権事項かもしれません。しかし、多くは兄弟間の長年の恨み・つらみです。本来は法律問題ではありません。残念ながら弁護士の本質として、争っている相手の方に寄り添う気持ちはないはずです。そんな時に両者の気持ちを和らげてくれる存在が居てほしいものです。人間の心などは時としてお金に傾きがちですが、気持ちの整理がいかに大切かと思います。しかし、弁護士以外の人の分割協議での報酬は、弁護士法違反になる恐れがあります。とはいえ、この精神的なアドバイス料は相当な額になると私は思います。それは、不動産業であれば、不動産のコンサルティング報酬として具体化しても良いと考えます。しかし、その他の業種、例えば保険業、証券業、FP、等の相続コンサルタントを称する人々は、何を拠り所に金銭を請求するのかという、永遠の課題に悩んでいることも確かです。
個人的な意見ですが、弁護士法や税理士法の分野を超える特別なアドバイスなどに、一定の報酬制度を認める法体系が望まれるところです。
それには「相続分野の国家資格制度」があっても然るべきです。

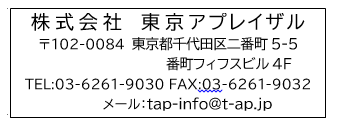
★YouTubeはじめました!チャンネル登録お願いします。
不動産鑑定士《芳賀則人の言いたい放題》 (別リンクに飛びます。)
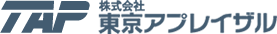

![[月いちコラム]芳賀則人の言いたい放題!](/wordpress/wp-content/uploads/side-blog02.png)
![[対談ブログ]こんにちは、芳賀則人です](/wordpress/wp-content/uploads/side-blog03.png)