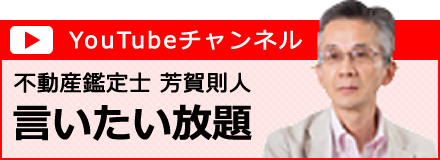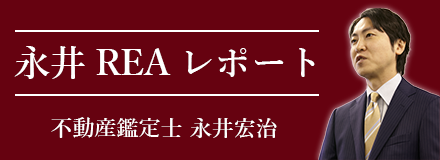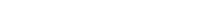税理士にとって、いわゆる「節税対策」という用語は、本来は禁句のようです。ある税理士は「適税対策」です、などという方もいます。とはいえ、我々税理士ではない士業にとってあるいは富裕層・経営者・所得の多い一般人にとって、本音を言えば税金が安く抑えられるのは歓迎すべきことです。
では、ここは割り切って相続の節税対策はどんな種類(商品といってもよい)があるのかざっくりと概観してみます。
1. 古典的・一般的なものとしてはハウスメーカー等が地主さんが所有する更地に賃貸マンション等の収益物件を建築させて、貸家建付け地(概ね更地評価の80%程度になる)にして評価減を計る。
2. 地主以外の富裕層は上記のような中古収益物件を借金(債務を作る)で購入して不動産評価の低減を利用するやり方
しかし、これがやり過ぎて、相続税を回避したと認定され令和4年4月19日最高裁判決により路線価評価を認めずに、時価評価(不動産鑑定評価による)により課税されたケースがあります。
3. タワーマンションによる節税対策
これは令和6年度の税制改正により、いわゆるタワーマンションの節税対策を封じ込める方策がとられました。古くは六本木タワーマンション事件があります。【国税不服審判所 裁決書平23第1号(平成23年7月1日)】
(概論)通達評価によらないことが正当として是認される特別な事情がある場合には、通達によらず、他の合理的な方式によって評価することが法22条に照らして許されるものとされました。
相続税申告時の評価 財産評価基本通達上の評価5,800万円。ところが、相続人は、被相続人死亡後4か月後に第三者に28,500万円で売却。この結果、通達上の評価は認められず、事実上売買価格が相続税評価額となりました。
4. 不動産特定共同事業(不特法)による小口化不動産の評価減額を狙った商品
これは、1棟物の収益物件(オフィスビル全体で20億円とする)を仮に200口(1口1,000万円)に分けて投資家に販売する方法。
都心部物件の配当利回りは3%程度ですが、家賃の下落がない昨今は異常なほど人気を博しています。特に魅力的なのは1,000万円で買った時の相続税評価額が、土地の持ち分が僅少でありかつ貸家建付け地に該当するため、何と150万円程度に圧縮されるのです。例えば、現金を保有する高齢者が10口買うとします。1億円の現金が小口化商品になると、その評価額が1,500万円になるのです。さあ、お立合いてなもんで、寅さんも驚く代物です。人気になるのもむべなるかなです。しかし、私の個人的意見ですが、このままこの制度が継続されるのかは疑問があると思っています。
5. 路線価評価(通達評価)と不動産鑑定評価
私の本業である不動産鑑定評価を、相続税の申告時に採用することが増えてきています。これはいわゆる節税対策ではありませんが、結果的には課税額が大幅に減少する効果があるので、冒頭に申し上げた「適税」といわせてもらいます。
長年(平成4年以来33年間)この業界でやって来ましたが、まだまだマニアックな世界から脱皮出来ていないのが実態です。本来は、土地評価は不動産鑑定士が本家なのですが、通達評価、独特の評価単位や地積規模の大きな宅地等のルールが異なる等で、不動産鑑定士が入りこめない事情があります。よって、適正な評価をめぐって様々な問題や困難さがあるのです。

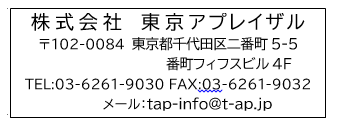
★YouTubeはじめました!チャンネル登録お願いします。
不動産鑑定士《芳賀則人の言いたい放題》 (別リンクに飛びます。)
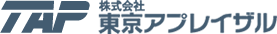

![[月いちコラム]芳賀則人の言いたい放題!](/wordpress/wp-content/uploads/side-blog02.png)
![[対談ブログ]こんにちは、芳賀則人です](/wordpress/wp-content/uploads/side-blog03.png)