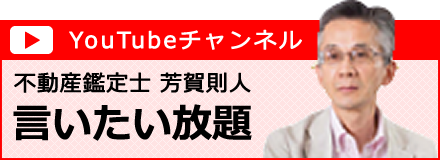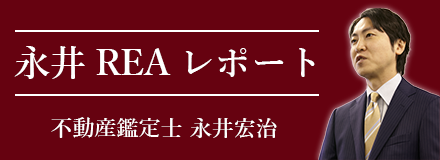専門家の役割には大きく分けて二つあると考えます。
- まず相談者の何が問題かをまず把握します。それによって相手に問題を気付かせて自ら処理あるいは対応できるかどうかの指針を提示します。一般の方はほとんど自分で処理出来ないことを理解します。
- よって専門家は解決への道筋を提案することになります。つまり相談者は納得して有料でコンサルや業務の依頼をすることになります。
次のような相続の相談をされました。ほとんどのケースで遺言書はありません。そうすると遺産を分けるのに際し、分割協議書を作成する必要があります。しかし、そもそも分割協議という言葉を知りません。日常的に使うことはないからです。さらに、どのような手続きが必要なのかも知らない方が多いのが実態です。
前号の問題です。
相続人は子供3人で母親(被相続人という)が亡くなりました。(父親は既に死去)遺言はありません。相続財産は自宅評価額(土地:路線価評価額+建物:固定資産税評価額)が3,000万円、預貯金1,500万円の計4,500万円です。
自宅には10年間母親の介護・面倒を見てきた長女63歳の夫婦が同居しています。他の相続人は次女60歳、次男57歳、
相続税の基礎控除は3,000万円+600万×3人=4,800万円なので相続税の申告義務はありません。
さて、相談先(専門家)は誰になるでしょうか。
相続のwebサイトを検索すれば山のような広告やHPを目にします。それによって「我が家には相続税は掛からないな」と知り、ホッとすることになります。
「税理士は必要ないか?であればだれが適任か?」と。
この程度であれば分割協議で揉めない前提で、数十万円の手数料で処理してくれる司法書士事務所(不動産の相続登記があるので)があるはずです。
と、思うのは専門家の悪いところで、いわゆる素人さんはそれも知りません。ここで、税理士事務所に相談する方も多いはずです。税務申告でナンボの税理士さんは、ちょっと計算すると相続税は出ないことにややがっかりします(ウチの仕事じゃないわと)。
で、断る税理士もいるでしょう。きっと。しかし、ちょっと待てよと。折角の相談なので、取りあえずウチで相談に乗り、知り合いの司法書士に回して上げようと考える人もいるはずです。このように目先の仕事になるのかならないのかで判断すべきでないと私は考えます。
今は直接の仕事にならないかもしれませんが、親切に対応すれば、例えば次女60歳の旦那さんの実家(仮に資産家とする)の相続に関与させてもらえるかもしれません。また、次男は大手金融機関に勤めていて、そこから巡り巡って仕事が来るかもしれません。つまり「いいご縁」を築けるチャンスです。
親切や優しさが専門家の第1条件とさえ言えるでしょう。

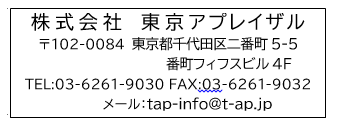
★YouTubeはじめました!チャンネル登録お願いします。
不動産鑑定士《芳賀則人の言いたい放題》 (別リンクに飛びます。)


![[月いちコラム]芳賀則人の言いたい放題!](/wp-content/uploads/side-blog02.png)
![[対談ブログ]こんにちは、芳賀則人です](/wp-content/uploads/side-blog03.png)