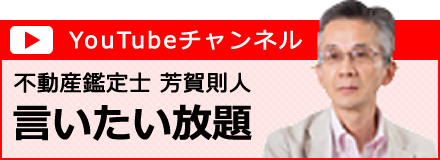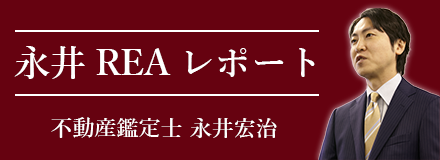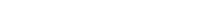~ 専門家の前に人であれ ~
最近はとみに感じることがあります。それは人のために仕事をするのが使命であるはずが、自分の利益を最大にすることが偉いという風潮を感じることです。
○○士という名称は、ほとんどが国家試験を合格した者に対しての称号であり、かくいう私も「不動産鑑定士」 「宅地建物取引士」 「相続診断士」(民間資格)等の名称を用いて仕事に従事しています。確かに儲けがないと生活が出来ないし、事務所も借りられない。適正な利潤は致し方ありません。しかし、その内容がいかなるものかを認識しているのかという疑問を感じる事案が多いのも事実です。
私は、常々、決して無理はするなと社員に口を酸っぱく(との表現はもう古いか)言っています。それは不動産鑑定士という職業は、物件の評価額の高目、低目の要求や要望の境で戦っているからです。よってウチは必ず相談から入ります。まず直接受けることはしません。
例を挙げます。A会社の社長から個人が所有する土地をA社(同族法人)に買ってもらうことになったとのことで相談があった。とします。
「先生、この物件の鑑定評価を鑑定料100万円でお願いします」といわれると、その誘惑に負けそうになります。仮にそれで受注したとします。
「社長、鑑定書出来上がりました。評価額は3億円になりました」と報告します。
「いやいや、先生、俺は2億円位になると思ったから依頼したんだよ。3億円の鑑定書ならいらないよ。何とか2億円にならないか?」といわれたとします。
そこで、「分かりました。では2億円の鑑定書を発行します」って、アリですか?
100万円の報酬を得るために無理して要求通りの鑑定評価書を発行したとします。
でも、もし、この鑑定評価が1年後の税務調査(低廉譲渡の疑義)で否認されたら、誰が責任取るのでしょう。それは不動産鑑定士に損害賠償が来ることもあり得ます。
当社はそれらのトラブルを避けるために、机上にて事前に概算評価を行い、ある程度の目線をつけます。当該例の場合は2億円~2億2000万円の概算評価を出します。それでよければ正式鑑定をお願いします。
「なるべく高い評価でお願いします」いや、「なるべく低い評価でお願いします」とは日常茶飯事です。もちろん、不動産評価はこれが絶対正しいということがないのが現実なのです。
【次回に続く】
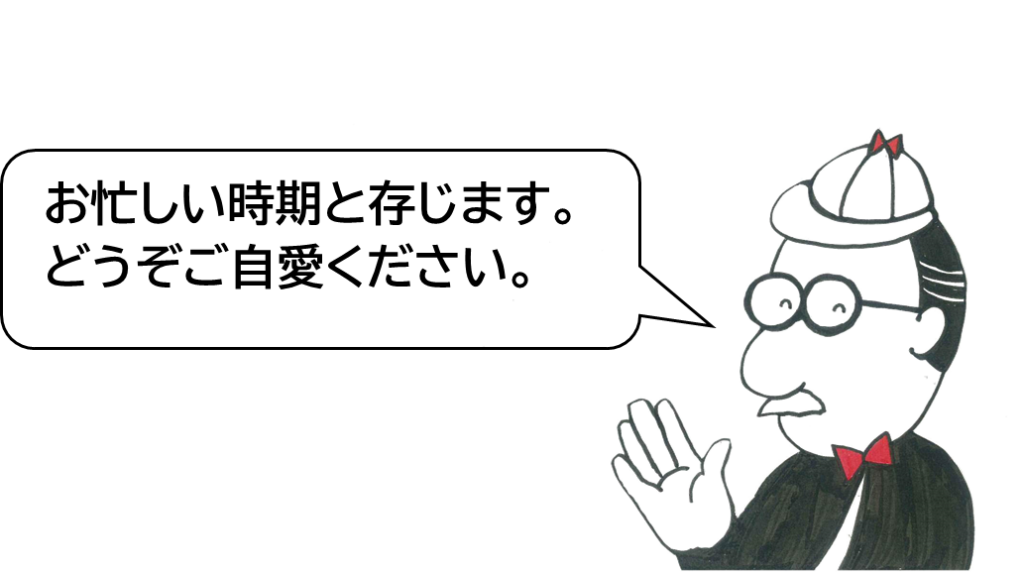
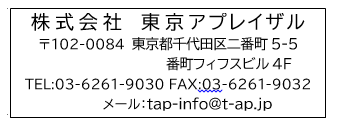
★YouTubeはじめました!チャンネル登録お願いします。
不動産鑑定士《芳賀則人の言いたい放題》 (別リンクに飛びます。)
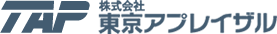

![[月いちコラム]芳賀則人の言いたい放題!](/wordpress/wp-content/uploads/side-blog02.png)
![[対談ブログ]こんにちは、芳賀則人です](/wordpress/wp-content/uploads/side-blog03.png)