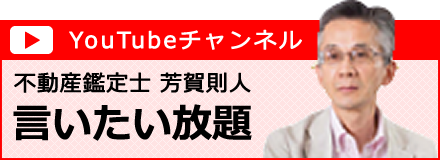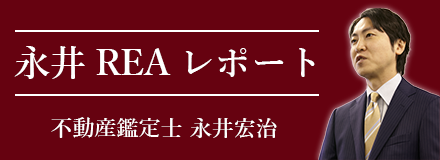東京アプレイザル・不動産鑑定士の永井宏治です。
前回では「士業における講師活動」のメリットを挙げましたが、詳しく考えていきたいと思います。
1.自社開催であったとしても「講師ができる専門家」ということで売りになる。
自社開催だとしても講師経験がそれなりにあると、「講師ができます」と対外的に言うことができます。私はAP-CADという弊社で販売しているCADソフトの講座を2013年から長年行ってきました。以前高田馬場に事務所があった時代は多い時は月に2回(入門、応用)講師を務めていました。コロナ前までそれを行っていたため、延べで100回前後は行ったと思います。また、税理士会支部研修、相続に関する団体、大手税理士法人様等で1度でも講師を行うと講師歴としてプロフィールに記載することができます。ここでのゼロか1かの差は大きいのではないかと思います。
2.自分でテーマを決めてレジュメを作成することで自分の頭を整理できる。
私は自社開催のセミナー講師が多いため、「このテーマでお話しください」と言われることはあまりありません(ビジネス会計人クラブ・大阪様のように外部からの依頼を受ける場合は別です)。相続土地評価アカデミーについても全て自分でテーマを決め、レジュメを作成することになるため、レジュメの構成も自分で考える必要があります。したがって、必然的に自分の頭を整理する必要があり、これは定期的な復習をする良い機会となります。
3.自身でレジュメを作成し講師を行うことで受け身ではなく「能動的に仕事を作っている」と意識することができる。
これは個人のタイプにもよると思いますが、私は比較的いろいろなことをやってみたい、と思うタイプです(とは言え、どうしても興味が持てないとか向いていないと思うことはできませんが…)。本業である鑑定評価はもちろん大事ですが、実務の中で養われたことを講師として話すこと、財産評価のCAD作図、業界誌への掲載、書籍執筆、このREAレポートの執筆等、不動産鑑定実務だけではなく、「不動産鑑定士」として実務に関連することを能動的に行いたいと考えています。
また、独立している士業の方なら「報酬をいただいて講師をする」ということは通常業務の外にある「イレギュラー」な仕事でありますが、独立したばかり等で最初は仕事がなかなか受注できない、という状況であれば単発の講師の仕事で収入が得られるならばありがたいことだと考えられます。
もちろん、講師を行う暇がないほど本業が忙しいならば講師を積極的に行う必要はないかもしれませんが、さまざまな士業の方のHP等を見ると講師経験を持つ方は本業外のイレギュラーな仕事も積極的に取り組まれている印象があります。
4.テーマを決めることで「自身がどのようなことを人に伝えたいのか」が認識できる。
やはり伝えたいテーマがあるからこそのセミナーだと思っています。私の場合、「相続土地評価アカデミー」は根底に適切な相続税土地評価を行うための知識を広めたい、という気持ちがあります。また、不動産鑑定士としての立場から土地の時価についてもっと知っていただきたい、という気持ちもあります。能動的に講師活動を行うことは、改めて「専門家としてどのようなことを人に伝えたいのか」を自覚するための良い機会にもなると思われます。
5.いくつかのテーマでレジュメを作成する場合、それが積み重なり将来的に業界誌への掲載、書籍の出版につながる可能性がある。
私は「不動産鑑定士が教える!相続税土地評価に生かすCAD作図術」という本を執筆しておりますが、この書籍の内容としてはほとんどが過去のセミナーレジュメや業界誌へ投稿した小論文を基にしたものです。2冊目の「相続 税土地評価における鑑定評価実例と裁決事例考察」は書籍を先に執筆し、現在の相続土地評価アカデミーの鑑定評価実例編、裁決事例考察編の実質的なテキストとなっております。書籍執筆とセミナーの順番は前後することもありますが、レジュメを作成することで業界誌への掲載や書籍の出版につながる可能性があり、より自身の専門家としての名前を広めるチャンスになると考えられます。
次回に続きます。

https://tap-seminar.jp/seminar.php?keyno=2333


![[月いちコラム]芳賀則人の言いたい放題!](/wp-content/uploads/side-blog02.png)
![[対談ブログ]こんにちは、芳賀則人です](/wp-content/uploads/side-blog03.png)